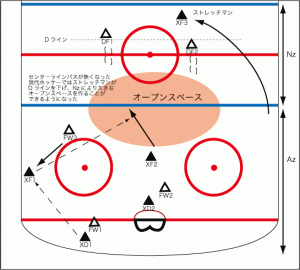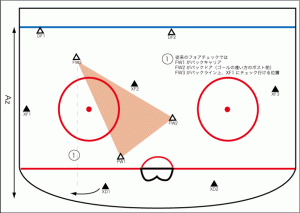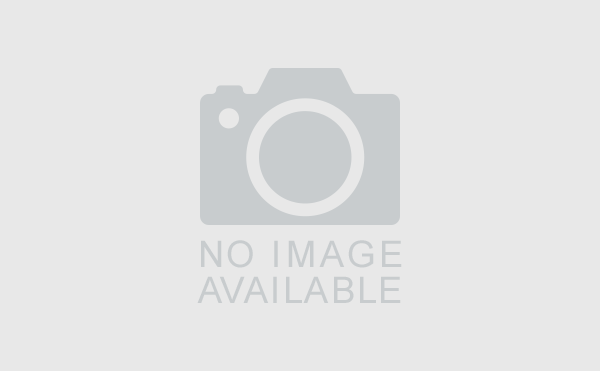1990年代の1−2−2フォアチェック
1990年代のホッケー、今と大きく違うのはセンターラインパスがあったこと。
センターラインパスとは攻め側のチームが2本のライン(Dzのブルーライン、Nzのセンターライン)をまたがってパスしてはいけないというルール。それにより長いパスからの攻めだし(英語ではブレイクアウトBreakOut)ができなかったんです。長いパスが使えないとカウンターになる確率が減るためフォアチェックは今以上にアグレッシブ(攻撃的)だったわけです。
その時代のフォアチェックについて解説します。
FW1が放り込んだパックに素早いフォアチェック
役目は相手Dを内側から外側に方向付ける(インサイドアウト)から最後はフィニッシュチェック(パックを出されてもボディチェックすることー和製英語ではアフターチェック)すること。
FW2はバックドア(ゴールの遠い方のポスト前)のポジション
役目は味方がパックを奪えた場合はゴール前のチャンスマンなる。もしくはFW1が相手Dに絡んだ場合はパックサポートをする。パックを奪えなかった場合、相手に攻め出しを許してしまった場合は仕事は無し。
FW3がパックライン上、XF1にチェック行ける位置のポジション
役目はパックを持つ相手Dの位置に合わせて(パックライン)ポジションを取りつつ、パスが出た瞬間素早く45度にフォアチェックをかける。逆サイドに展開された場合は仕事無し、強いて言えばバックチェック(自分の守りのエリアに一生懸命戻ること)をすることぐらいですね。
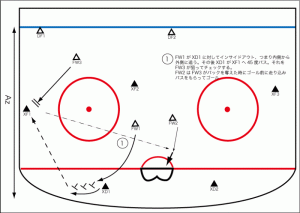
この1-2-2フォアチェックの長所
相手Dが攻撃側の思惑通りインサイドからアウトサイドに方向づけられつつ、思惑通りに45度にパスを出してくれることいよって、最大限の威力を発揮する。
この1-2-2フォアチェックの短所
自分たちの思惑とは違い、逆サイドに展開された場合、図のように不意を突かれたチェックがすべて後追い、穴だらけのフォアチェックになる。逆サイドに展開された場合、つまり思惑通りに行かな買った場合は諦めて下がればいいんだけど、傷を埋めようとして大怪我するんですよね。
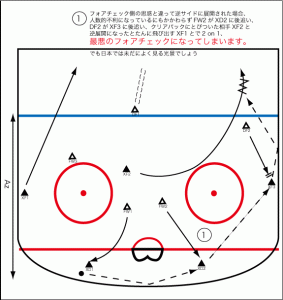
なかじの総評
センターラインパスルールがあった1990年代にはこのフォアチェックで世界一と言われたカナダ、それをお手本に日本でもこのフォアチェックに取り組んだ。情報不足か理解不足か日本では定義付けが今イチ甘かったので各状況による対応ができなかった。とくに逆サイド展開された時は本当にもろいフォアチェックだったのにも関わらず説明、理解、対策無しに今まで来ている。
センターラインパスが無くなった2000年代のホッケーでは、世界どこにもこの攻撃的フォアチェックを使っている国はいない。ストレッチマンがオープンスペースを大きく作り、攻め出し側が絶対有利になったためだ。一人一人の仕事が大切なホッケーでFW2が味方がパックを奪った時にしか仕事が無いというのはもったいない。
そしてもう一点、失点をしないカウンターを与えない現代のホッケーでディフェンスがAzの45度に詰めることはもうしない。英語で「ノーピンチングNo Pinching-Dが45度を詰めない合い言葉みたいなものになってる」といってカナダではどのコーチも試合前にDにその指示をしています。この1-2-2では逆サイド展開された場合45度はDが行くケースが多い。世界はもうNO PINCHING!! なんです。
というわけで、1990年代の最も使われた1-2-2フォアチェックとして思い出の中にしまうべきシステムだと考えます。